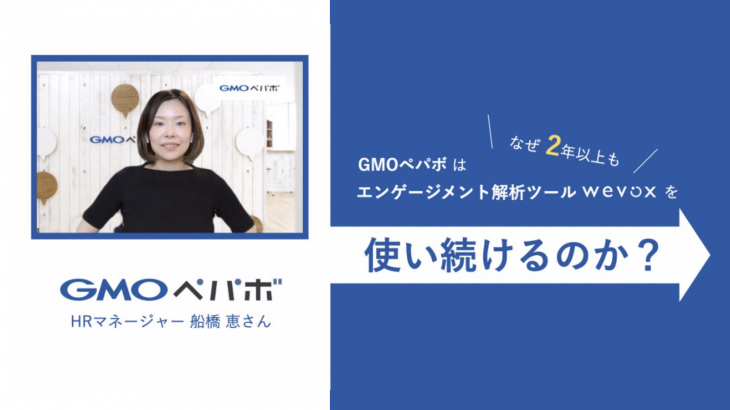リード実践的な組織づくり戦略や組織改善プラットフォーム「wevox」の活用方法を紹介する「活用事例シリーズ」。今回お話を伺ったのは、株式会社フジクラの若手社員の皆さま。エネルギー事業や自動車電装を行う明治からの老舗企業・フジクラでは、若手社員の発案がきっかけでwevoxが運用されています。日系の大手企業で、若手が主体となってどのように組織を変えてきたのか。wevoxの活用方法、組織文化の作り方、将来の理想像まで、幅広くお話を聞いてきました!
人間関係はいいのに、イキイキと働けていないのはなぜだろう?
−フジクラさんでは、若手メンバーの提案がきっかけでwevoxの導入が決まり、現在もご活用いただいていると聞いています。今日は導入に至る話や、どのように活用しているのかをお聞かせください。
(田原)率直に言ってしまうと、私自身が「もっと社内をワクワクできる雰囲気にしたい」と思ったのがきっかけなんです。当社は連結での社員数が5万人を超え、設立から100年以上を経過しているトラディショナルな大企業です。昔からの組織風土で、仕事がトップダウンで降りてくることが多く、僕らのような20代のメンバーにとっては、自分のコントロール外のところでいろんなことが発生する状況だったんです。
(富田)結果、どうしても若手を中心にモチベーションが下がる傾向にありました。それが当たり前だ、という風潮も一部にはあって、若手も受け入れざるを得ない状況でした。
(田原)そんな雰囲気を、自分たちがアクションを起こすことで変えられないかな…と思ったんです。それで、上司に提案できることはないかと考え始めました。アクションを起こすためには仲間を増やそうと思い、私の教育担当だった富田に相談したのが最初ですね。
−その時点でwevoxはご存知だったのですか?
(田原)wevox自体は、知人から話を聞いていて知っていました。ただ、他社さんのサービスも含めて比較検討して、wevoxに決めています。そもそも、なぜエンゲージメントサーベイだったのかというと、自分たちの部署が抱えている問題を可視化したいと思ったからなんです。
(富田)田原から相談されたときに感じたのは、「確かに空気はあまり良くないよね…」ということでした。薄々みんな気付いているのに、理由はよく分からない。だったら、まずは原因を理解して共有し、何かアクションにつなげていけたらいいよねと話し合ったんです。
(田原)ただ、はっきりしておきたいのは、人間関係はめちゃくちゃいい組織なんです。なのに、イキイキと働けていないことが引っ掛かっていて、それを何とかしたいと思いました。それで社内の状態を知ろうと考えて、wevoxに興味を持ちました。

若手メンバー全員の「やりたい」の声でwevoxの導入が決定
−どういう流れで導入につなげていったのでしょうか?
(田原)最初は上司にちょこちょこと相談していました。wevoxを提案するにあたり、まず懸念したのは費用面です。当時は部署のメンバーが11人だったのですが、wevoxであればそれほど金額は高くない。提案しやすいと思いました。
(富田)感じている課題についてまとめ、なぜwevoxを導入するのか、どのような運用をしていくのか、といったことを若手で資料にまとめ、上司に提案したんです。
−上司の最初の反応はどうだったのでしょうか?
(田原)前向きにちゃんと話を聞いていただけて、最終的には「若手メンバー全員が本当にやりたいというのなら導入してもいい」と言っていただきました。

上司が心配したのは、どれだけいいものであっても、やりたくない人がいるかもしれないということでした。そこから、若手メンバー全員に話をしていったんです。みんなからすごくいい反応をもらって、これはいけるぞ、と。
(栗田)私が最初に話を聞いたときは、「よくぞ言ってくれた!」と思いました(笑)。
(田原)話を聞くと、どうやらみんな共感するところはあったようで、みんなすごく前向きに考えてくれましたね。最終的には、毎週行っている朝会の場に資料を持ちこんで、プレゼンしました。結果、その場でやろうという話になったんです。内部的に部長の承認だけで進めていいのかを確認するために企画の部署にも確認して、問題ないとの判断だったので正式に導入が決定しました。
組織について話す文化が1ミリもなかった組織が、少しずつ変わり始める
−最初はトライアルでの実施だと思うのですが、いかがでしたか?
(田原)1回目のサーベイが3月末でしたが、出たスコアを見たときは「ああ…」という感じでしたね。
(富田)想定はしていたんですが、すごく低かったんですよ。でも、「まあ、そうだよね」と。想定通りといえば想定通り。だから、「やることがいっぱいあるね」という話をしましたよね。部長からしたら、スコアが低いわけですから心象は良くなかったと思いますが…。
(田原)ただ、部長は結果を見て「どこが悪いかが見えてくるのは面白いね」とは言ってくれましたね。
−実施の頻度は?
(田原)週1回の運用です。海外営業部なので日本にいないメンバーも多く、特に部長などマネジメント層はどこにいるのかわからないくらい忙しくされているので、業務の負担にならないように、負担を減らそうと思ったからです。
−スコアを見て、前向きに改善していこうという流れはすぐにできましたか?
(富田)最初はなかなかそうはいきませんでした。でも、スコアを見て「ああ、そっか」で終わってしまっては意味がないので、まずはワークショップをやろうという話しになったんです。とにかく、まずはみんなの意識を同じ方向に向けることを考えて、問題意識の共有から行いました。

(田原)うちはお話しした通り昔ながらの会社で、実はこれまで組織について話す文化が1ミリもなかったんです。だから、wevoxの結果を見ても、正直なところみんなどうしたらいいのかもよく分からなかったと思うんです。ただ、恥ずかしい状況であることは間違いないわけで、まずは土壌づくりというか、組織について考えることに慣れさせるところから始めたという感じですね。
−結果については想定の範囲内だったとのことですが、具体的に教えていただけますか?
(田原)項目でいうと、「人間関係」と「健康状態」は絶対に高いだろうなと思ったら、その通りでした。本当にうちの部署はみんな仲が良くて、上長も含めて気軽に相談できる雰囲気があるんです。ただ、弱いはずだと思っていてその通りだったのが「理念戦略」や「事業への納得感」、あとは「経営者への信頼」という項目です。
−皆さんの中でも納得感はあったのですか?
(富田)ありましたね。みんな同じような気持ちだったと思います。
(田原)良かったのは「数値化」できたことです。みんなが思っていたとしても、「それはお前の主観だろう」と言われたらそれまでです。でも客観的なデータになれば、一発で共有できます。特に上のレイヤーの人ほど、数字で伝えないと納得してもらえませんよね。
組織のいいところ・悪いところを皆で挙げてみると…
−何か具体的な施策は打ったのでしょうか?
(田原)簡単なものからですね。前提として、運用については誰かに権力が集まるような仕組みにはしたくなかったので、メインは僕ら3人になりますが、できるだけ分散させて若手中心で回すようにしました。最初から考えていた毎月1回のワークショップも、全員が関われるようなものにと考えました。
(富田)この3人主導で進めてしまうと、みんなに問題意識が共有化されないかもしれないと思いました。元々、組織について考える習慣がなかったわけですから、人任せになるのは嫌だったんです。だから、ワークショップのファシリテーターは指名制にして、できるだけいろんな人にやってもらうようにしました。
(田原)施策は、最初は始めやすいものからです。それこそ、職場の雰囲気が暗いなら「大きな声で挨拶をしよう」とか。自分たちでできることからまずは始めようと。あとは緩い飲み会を開催するとか、そんなところから始めましたね。
(栗田)初回のワークショップでは、アトラエさんのセミナーで教えていただいた「KPT」のフレームワークは活用させてもらいました。組織について考える入り口として、まずは「良いところ」「悪いところ」を書いて整理してみる、みたいなところから始めましたね。
−意見は出ましたか?
(田原)特に事前に考えてきてもらったわけではないのですが、思ったよりもかなりの数の意見が出ましたね。それぞれ、思っていることは多かったのかもしれません。やってみてよかったです。
(富田)あとは、「カジュアルフライデー」ね。
(田原)あれは、施策ですかね? 内勤でもスーツを着るのが当たり前だったので、風穴を空けようと私が1日だけチノパンで出社しただけです(笑)
(富田)ワークショップの時に、夏は暑いのでポロシャツでもいいという話になったんですよね。
(田原)部長には「金曜だけにしような」って(笑)。大事なのは「小さな反抗心」というか。みんながスーツを着ていると、それで思考停止しちゃうじゃないですか。でも、一人でも変なことをやっている奴がいたら、何かピリッとくるかなと思ったんです。
(栗田)それでいうと、うちはフレックス制が導入されているにもかかわらず形骸化していたんです。それで田原さんが使い始めたら、だんだん広がってきて、今は10時出社でも何も言われなくなりましたよね。
(田原)最初は「重役出勤」なんて言われましたけどね(笑)。
(栗田)まだ使っているのは若手が中心ですが、これは大きな変化の1つだと思います。

「世代間でギャップがある」ことを、お互いに認識できるようになった
(富田)施策の話に戻すと、アトラエさんのワークショップに参加して色々な企業さんと情報交換をしたときに、1on1をやってなかったのがうちだけだったんです。だから、絶対に始めようと思って、すぐに部内で提案しましたね。やってみようという話になって、上長とは2週間に1回、教育担当とは毎週1回、実施するようになりました。
−それは大きな変化でしたね。
(富田)何より、コミュニケーションの量が劇的に増えました。相互理解が深まるきっかけになったと感じています。
(栗田)その次のワークショップでも、みなさんから「続けたい」という声が上がりましたよね。みんなも何かしら効果を感じているんだなと思いました。
(富田)あとは、部署のミッション、ビジョン、バリューを策定しました。

(田原)きっかけは、あまりにも「理念戦略」の項目のスコアが低かったこと。これは長期的に見て絶対にボトルネックになると思ったんです。会社が掲げるものはしっかりとあるんですが、正直ちょっと自分ごととして落とし込むには遠かったんですね。ならば、部の独自のものをみんなで考えようということになりました。
(富田)最初は「そもそもミッションとは何?」からですね。上司が「キングダム」が好きなので「キングダムで当てはめるとこういうことです」みたいな資料を作りました。
(栗田)あの資料のおかげで、だいぶみんなの理解は進みましたよね(笑)
(富田)最初の月がミッション、次月にビジョン、その次の月にバリュー、というふうに進め、実際に策定したものは壁に貼ってみんなが見えるようにしています。
(田原)作ることも大事ですが、みんなで考えて意見を出し合えたことも良かったと思っています。実際、理念戦略の項目のスコアはどんどん上がっていますからね。

−そもそも組織について考えなかったところから比べたら、すごい変化ですよね。他に、目に見えて変わってきていることはありますか?
(田原)圧倒的にコミュニケーション量は増えましたよね。仕事の話だけのときと比べて、お互いを知る機会が増えたのは一番大きいです。
(富田)若手メンバーたちは以前から、年代間でギャップがあることを分かっていたんです。1on1やワークショップを通じて、上の方々もギャップを認識し始めてくれたことが、個人的には最も大きな変化だと思っています。コミュニケーションが増えた今、そのギャップを埋める作業が少しずつですができ始めていると感じますね。
(栗田)先日、アトラエさんのワークショップに上司と一緒に参加させてもらったんです。これまでは社内だけの話でしたが、他の企業さんと交流したり、うちの話を「いい取り組みですね」なんて評価していただけたのは、すごく大きな体験だったと上司自身も言っていました。そこから、上司が少し変わった気がしているんですよ。
(田原)ちょうどそのワークショップの日、私は海外出張だったんです。夜、いきなりイベントに参加した上司から電話がかかってきて、「wevox、もっと頑張ろうな!」って。突然ですよ。何があったんだと驚きましたけど(笑)、嬉しかったですね。
−実際に変化も感じられて、間違いなく今回の取り組みは皆さんにとっての1つの成功体験になったのではないですか?
(富田)それは間違いないですね。成果も出始めているので、やりがいにもなっています。ただ、もうワンランクくらい進められたところで、ようやく達成感が持てるのかなと思います。
(田原)まだまだ道半ばですね。
エンゲージメントに興味を持つ人を社内に少しずつ増やしていきたい
−1つの部署でこれだけ取り組みが進んでいると、他の部署の反応ってどんな感じなんですか?
(栗田)周りの部署の人から、「仲が良いよね」と言われることは増えましたね。
(田原)ぶっちゃけていうと、狙ったほどはみんな反応してくれてないです(笑)。
(富田)周知がまだまだなんですよね、きっと。
(田原)だから、これからはそのフェーズだと思っています。もっと社内で取り組みを伝えていくとか、興味を持ってもらうための取り組みも考えていきたいと思っています。その時に、数字的にはまだまだではありますが、最初に比べたら格段にスコアが上がっているわけですから、このデータを持って伝えていけると拡散も早いのかな、と。
−同様に取り組んでみたい企業さんに対して、何かアドバイスはありますか?
(田原)本当にやりたいと思う人がやらないと、回らないし続かないと思いますね。
(栗田)キーパーソンを探して、うまく巻き込んでいくことでしょうか。私たちの場合は若手メンバー全員が団結できたのが大きかったですし、加えて部長や上司も協力的でしたから。
(田原)そうなんですよね。たまたま僕らは「みんなでやろう」とうまく盛り上げられましたが、今後、他部署に展開していきたいと考えたときに、売り込もうとすると失敗すると思うんです。強制するものではないというか。まずは目に触れる機会を増やしながら、興味を持つ人を増やすことが大事なのかなと感じています。
−では最後に、皆さんが目指す「理想の組織像」について教えてください。
(富田)wevoxを使い始めてから、コミュニケーションの大事さがよくわかりました。人間ですから、それぞれ思うことも目指す方向性も違って当然ではありますが、組織としては同じ方向を向いて働ければ決定スピードも早まりますし、腑に落ちる決定がされる機会は増えると思うんです。まずはうちの部署がそうなりたいですし、それが全社的に広がれば、会社そのものが変わっていくことにもつながるはず。そのためには、粘り強く続けていくことが大事かなと思います。
(田原)シンプルに、楽しく働ける人をもっと増やしたいですよね。ため息をついている上司の姿は見たくないですし、楽しく働けるメンバーが1人でも多くいる組織にしたいです。じゃあ楽しく働けるって何だと考えると、「自分で意思決定できる」とか「人間関係がいい」とか、そういうことの積み重ねだと思います。wevoxで組織の状態に目を向けながら、引き続きできることを考えていきたいです。

(栗田)エンゲージメントの考え方が福利厚生の1つになって、もっとみんなが考えるようになったらいいなと思っています。以前参加したイベントで、「福利厚生を充実させたのに離職率が下がらない」という話をしていた人がいたんですが、その時の感じたのが、組織を動かすドライバー、テコになるのはエンゲージメントではないかということです。
福利厚生は確かに大事ですが、それに加えてエンゲージメントにも目を向けられる組織になれば、もっと働きやすい環境を作れると思います。
(富田)私たちの取り組みを伝えていくことが、その一助になれば嬉しいですよね。伝染病のように、少しずつ伝えていければと。
(栗田)現時点では、社内だけで見たら「あそこは何やら変なことをしているな」という感じかもしれません。ただ、社外に目を向けると「すごく当たり前」のことをしていて、しかも他社だと上の人たちや人事が率先して危機感を持って取り入れています。それを伝えていくだけでも、エンゲージメントに対する社内の意識は変わっていくのかもしれないと感じています。


 エネルギー・情報通信カンパニー
エネルギー・情報通信カンパニー エネルギー・情報通信カンパニー
エネルギー・情報通信カンパニー エネルギー・情報通信カンパニー
エネルギー・情報通信カンパニー